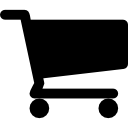The latest at
Mountain Equipment

小春日和のプチフィールドテスト
私たちMOUNTAIN EQUIPMENT 正規代理店である株式会社双進アクシーズクイン事業部では定期的にフィールドでのサンプルテストを行っています。
まだアウトドアのフィールドへ出ることが今ほど厳しくなかった3月の中旬頃、新鮮な花粉が溢れる小春日和に(花粉症にはとても辛い!)のんびりとテスト、撮影を行いに近郊の山へ繰り出しました。

小春日和ではあるものの、風が強くて少し冷えるので手首のベルクロをしっかり締めて冷えを防ぎます。体が冷える前に対策することが重要ですね。
やや動きがカタいカメラ慣れしていない生産輸入管理のY島。

スズタケに囲まれた道を上がって行くと、すぐに体が温まって汗が吹き出してきます。先週も別の山へ撮影に行っていたので二週連続の山行。すっかりカラダは山仕様に仕上がっていて絶好調!
ジャケット:CLASSIC WIND JACKET
パンツ:BIG POCKET PANT
バックパック:OGRE42

もはやME春夏シーズンの顔となった”CLASSIC WIND JACKET” コットンのような風合いでいながらナイロン100%で、防風性、携帯性、耐摩耗性に優れ、3シーズンの登山にはピッタリのウィンドシェル。このナチュラルな風合いが森の中の登山に自然に溶け込みます。

木漏れ日が気持ち良いトレイル。しかしながら花粉がヒドイので「ハクション!ハクション」と10秒ごとにくしゃみをしながらトレイルを歩いていきます。
撮るのは慣れているが撮られるのは慣れていないPRのO川。
撮影も兼ねているのでいい場所を見つけてはパチリパチリと撮影をする。そのせいで山と高原地図のコースタイムより大幅に遅れをとりながら進んで行く。

ジャケット:SQUALL HOODED JACKET
パンツ:ORION PANT
バックパック:OGRE33
キャップ:YOSEMITE CAP
SQUALL HOODED JACKETは昨年復活を果たした待望のソフトシェルジャケット。MEのオリジナルソフトシェル素材 EXOLITE はとてもソフトでノイズレス。防風性、通気性、ストレッチ性を持ち、テクニカルなクライミングからトレッキングまで幅広くこなすマルチプレーヤー。経年による劣化が少ないのも特徴なので長く愛用できます。着用カラーのAcidは明るすぎないナチュラルイエロー。イチオシカラーです。

しばらく道なりに進むとメインの登山道と合流。さらに進んで山頂は早々にスルー。そこから一般登山道を外れて易しいバリエーションルートに入って行く。超易しいバリエーションルートとはいえ、道が不明瞭であったり、倒木が何本もあったりと、一般登山道とはやはり雰囲気が違う。


まったく人の通らない道をずんずん進み、予め地図で調べておいたランチスポットへ到着。どっかりと地面に腰を下ろしてくつろぐ。雑なオトコメシですみません。。
さて、ここで今期の注目アイテムをご紹介。
“BIG POCKET PANT”


インナーポケット

外側のビックポケット
もともとはクライミング向けに作られたパンツで、左右に配置されたBIG POCKET にはクライミングシューズがすっぽり入ります。実際のクライミングではシューズがポケットに入ることで岩場の移動がとてもスムーズになります。
速乾性と運動性を持ち合わせているので、今回はトレッキングでテスト。足上げはスムーズ、じっとりとかいた汗もいつの間にか乾いていました。実はスノートレッキングでも既にテストしてまして、撥水性が高く、アンダータイツと合わせればオールシーズンで着用可能です。
男女兼用XSからの作りなので女性にもオススメ!
“CLASSIC WIND JACKET”


着まわしやすいレトロシリーズのウィンドシェル。気温差が激しい春秋にとても重宝します。サラリと羽織って寒さを軽減し、脱いだ時にはコンパクト。ザックの中に忍ばせておくと役に立ちます。
こちらは男性用、女性用共にあり。
女性用はコチラ。
“SQUALL HOODED JACKET”


最大の特徴はオフセットされたフロントジッパー。風を防ぐための高い襟が顎に干渉しないためのものですが、見た目の見た目の好印象にもつながるアクセントの効いたデザイン。
兄弟モデルの“ECHO HOODED JACKET”は同じ素材のストレートジップ、3ポケット仕様でより扱いやすくなってます。
MOUNTAIN EQUIPMENTは山を楽しむ女性クライマー&ハイカーを応援していますのでこちらも女性用あり。
女性用はコチラ。
これらのモデルはMOUNTAIN EQUIPMENT 取扱店、MOUNTAIN EQUIPMENT WEB STOREにてご覧いただけます。是非店頭、WEB上で足を止めてご覧ください!
ちなみにこの後は一日の花粉吸引量が限界を超えたので、持参したウェアや道具の撮影を行い速やかに下山しました。この後鼻水の出過ぎで鼻のあたりが痛くなってしまったのは言うまでもありませんね。